|
1.はじめに
『水』は私たちの生活に欠かすことのできない大切なもので『給水』は『電気』『ガス』と並ぶ重要なライフラインの一つとなっています。
一方、我が国は地震大国であり、残念ながら突然予想のできない大地震が発生してしまうことが十分考えられます。
ひとたび地震が発生するとライフラインの切断が想定されますが、復旧には相当時間が必要となり、場合によっては数日から1週間以上かかることもあります。
このため、生活に不可欠なライフラインには何らかの安全処置を確実に講ずる必要があり、『給水』の場合には受水槽に蓄えられた『水』の有効活用もその一つです。そこで地震発生時に配管破損しても受水槽の『水の流出』を防いで生活に必要な最低限の水を確保するためのバルブである受水槽用の「緊急遮断弁」を紹介します。
2.給水での緊急遮断弁について
昨今、一般的に受水槽を経由しない直結給水方式が主流となっています。この方式は、衛生面、工事費の削減、給水設備の省スペース化などで注目され、圧力が不足する場合には増圧直結給水ポンプが使用されています。
しかし、直結給水方式の場合、事故や地震などの発生により断水することがあります。断水後、即座に復旧できればよいですが、予想以上の大きな地震が原因の場合、復旧までに時間が必要となります。
一方、受水槽方式の場合、一定量の水が確保されており、災害時はその水を利用することを想定していました。しかし、阪神淡路大震災では受水槽以降の配管の破損により、いざという時に確保されているはずの水が流出し、復旧までに生活用水の確保に苦労するということがありました。
この経験から学び、翌年発行の建設大臣官房官庁営繕部監修(社)公共建築協会発行「管庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」では、受水タンク廻り、給水管分岐部に緊急遮断弁の設置例を掲載しました。
同様に(社)公共建築協会発行の「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成19年度版 施工66 受水タンク廻り配管要領(図1)にも「緊急遮断弁」の設置例が掲載されました。
また、災害時の緊急本部となる公共施設、地域の避難場所となる公立学校では受水槽を設置し、さらに受水槽出口の配管に「緊急遮断弁」を取り付け、地震発生時に閉止させることで、確実に水を確保できる対策を進めています。
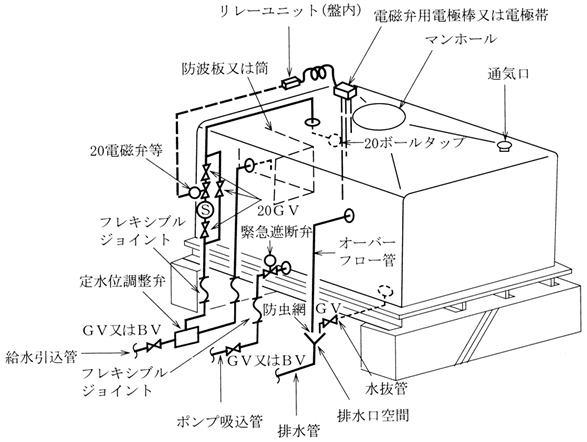
|
図1 受水タンク廻り配管要領 |
3.受水槽用緊急遮断弁の作動
受水槽用の「緊急遮断弁」は感震器を内蔵した制御盤(図2)が地震を感知すると、弁閉信号を出力して受水槽出口に取り付けた遮断弁を閉止して受水槽内の水を確実に確保します。
また、制御盤には地震による停電に対応できるよう、バックアップ用のバッテリー、給水ポンプを停止するための接点や外部警報用の接点を内蔵しています。感震器の設定震度は、一般的に配管の強度が保つことができる経験値で「200ガル(震度5強)」で作動するように設定されています。
「緊急遮断弁」の種類には、電気信号で遮断・手動による復旧方式の電磁緊急遮断弁(図3)と、電気信号で遮断・自動による復旧方式の電動緊急遮断弁(図4)、バタフライ式電動緊急遮断弁(スプリング閉式)(図5)さらに感震器からの作動時の機械的出力で直接弁を遮断・手動復帰の機械式緊急遮断弁(図6)があります。
定水位弁などの受水槽廻りの自動弁類を図7に示します。
 |
 |
| 図2 制御盤 |
図3 電磁緊急遮断弁 |
 |
 |
| 図4 電動緊急遮断弁 |
図5 バタフライ式電動緊急遮断弁
(スプリングリターン) |
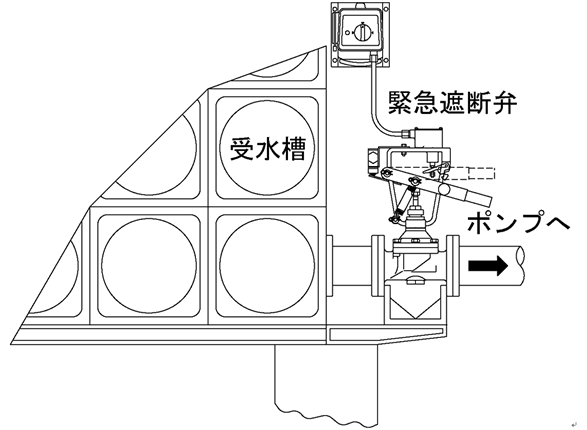 |
| 図6 機械式緊急遮断弁 |
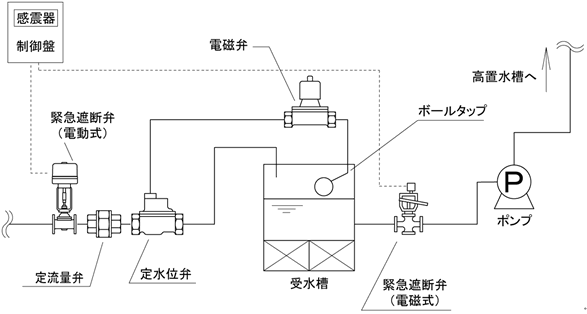 |
| 図7 受水槽廻りの自動弁類 |
手動復旧方式の電磁緊急遮断弁は、復旧(弁開)時に感震器をリセットした後に、緊急遮断弁以降の配管が破損していないか等の安全確認を人が行ってから弁開作動を行います。これにより電源復旧で自動的に弁開して、確保された水が流出してしまうことありません。
これに対し、電動緊急遮断弁は、制御盤内蔵の感震器をリセットして復旧(弁開)ボタンを押せば自動的に弁が開くため、復旧操作を行う前に配管に異常がないか十分チェックする必要があります。
全体的なシステムフローを図8に示します。
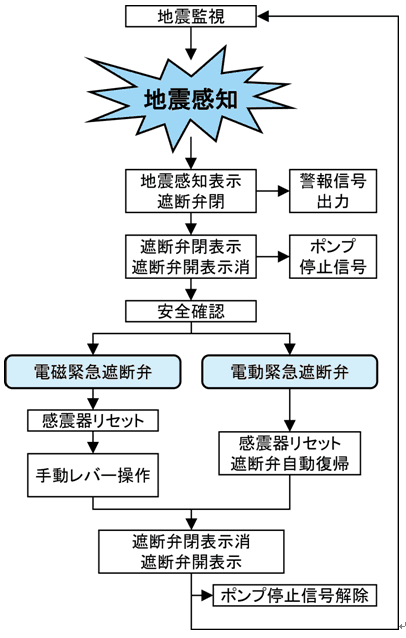 |
| 図8 緊急遮断弁システムフロー |
「緊急遮断弁」は受水槽出口に設置されることが一般的ですが、さらに入口にも設置することで汚水流入防止に対する安全性が向上します。
但し、一般的に給水圧が高くなるため急閉時のウォータハンマも考慮する必要があります。電動弁タイプは電磁式に比べ弁閉スピードが緩慢なので受水槽入口には電動弁タイプが適しています。
機械式緊急遮断弁は電気工事を必要としないため、既存の受水槽に設置するのに最適な遮断弁といえます。
これら給水で使用される「緊急遮断弁」の接液部には錆びの発生しない材料を選定する必要があります。
4.最後に
緊急遮断弁を利用した安全確保について紹介しましたが、地震のようにいつ何どき起きるか想定できない現代社会ではライフライン確保のために確実な安全システムを構築しておく必要があります。
また、システムを確立しても、いざという時に活用できなければ意味をなさないため、定期的なメンテナンスや作動確認が非常に重要になりますので、確実な定期点検スケジュールを立案・実行していただくことをお願いいたします。
以上 |