給排水設備の専有・共用一体的改修について |
平成26年4月1日
株式会社長谷工コーポレーション 山鹿 英雄 |
|
(図は、クリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
改修の現状と課題
給排水設備の改修としては、給排水配管の経年劣化による更新がある。給水配管工事については配管材料として長く金属管が使用されており、昭和40年代以降については、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管が規格化され多くのマンションで使用されていた。この配管により直管部分の錆の発生は無くなったが、継手部や継手接合部の腐食が経年劣化による不具合と相まって赤水の発生や漏水事故が生じ、築30年を超えるマンションではライニング鋼管の更新時期を向かえている。
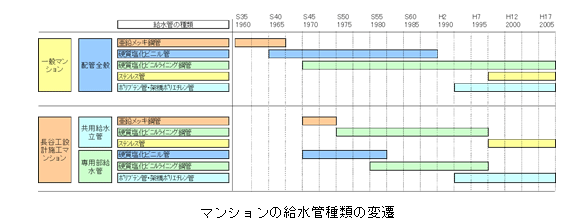
更新手法として更新と更生があるか、更生工法は管内面を再ライニングする工法が一般的である。この工法は、老朽化した水道管の更生工法として生まれた工法であり、1971年に日本水道協会よりJWWA「水道用タールエポキシ樹脂塗装工法」として規格化された。サンドブラストや研磨材を利用して給水管内の錆こぶを除去し、人体に無害なエポキシ樹脂を塗布(ライニング)して、管の再生延命化を行う最もポピュラーな工事である。給水管更生工事は事前の調査、診断が重要であり、給水管の残存肉厚がある程度確保されていることが条件である。また、環境ホルモン等の流出等、人に対して安心・安全であること確認して更生工法を選定する必要がある。
更生工事を実施した場合でも、数十年後、再度工事が必要となること及び直結増圧等の給水システム変更が許可されないことから最近は更新工事を選択する管理組合が多い。
更新工事における給水管材は耐久性が高く、将来的な維持メンテナンスの負担が少ない「ステンレス配管」や「ポリエチレン配管」を採用する事例が多い。
配管の経年劣化は同一の管種を使用している場合、共用、専有を問わず見られる現象であり、共用部改修時期に合わせて、専有部の更新を計画する管理組合が見られるが、区分所有の問題から専有部の更新については個々に任されているのが現状である。しかしながら、漏水によって被害があるのは階下の居住者であることから、建物全体の問題として検討をしていかなければならない課題である。
(有)マンションライフパートナーズの柳下氏の著書「マンションを長持ちさせる設備改修ノウハウ」に専有部の給水管・給湯管を管理組合が一斉に更新する場合の一般的な考え方として、下記の6点を挙げている。この著書は設備改修に対して参考となる点が多いので是非一読をお勧めしたい。
- 共用部分と専有部分の配管はつながっていて、同じ管材が使われ、劣化の状況もほぼ同じである
- 各戸の更新に判断をゆだねてしまっては、管理が行き届かない。
- 専有給水管が腐食し漏水が発生した場合、困るのはその下階住戸である。
- 配管の老朽化の問題は、全戸共通の課題であり、管理組合で取りまとめたほうが合理的である。
- 専有給水管の管理や更新と言われても、専門知識を持ち合わせていない居住者としては、どうしていいか分からない。
- 管理組合で取りまとめ、全戸一斉に更新したほうが、スケールメリットにより工事費が安くなる。管理組合であればコンサルタントも雇えるので、適切な修繕が実施できる。
排水設備については、排水立て管が経年劣化による更新時期を向かえていても更新が行われていないのは、共用設備であるにもかかわらず専有部を貫通しているための工事の煩雑さや同意形成の困難さによるところが原因である。
築後30年を経過したマンションが100万戸を超え、排水管の更新が必要なマンションが確実に増加している。特に排水管材として配管用炭素鋼鋼管(白ガス管)やコーティング鋼管を採用しているマンションは、接合部分の腐食が進行していると想定されることから、漏水事故のリスクを回避するために専門業者による調査診断を受けること検討すべきである。
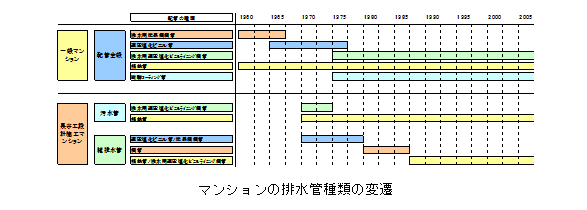
また最近多く発生しているのが、立て管との合流部からの漏水である。排水管は管内部にスライムが付着するため1年1回もしくは2年に1回定期的な清掃を行っている。この際、高圧洗浄による洗浄方式を採用しているケースがほとんどであるが、洗浄ホースにステンレスワイヤーメッシュホースを用い洗浄を行うと、立て管との合流部分が洗浄痕として削れてしまい穴が開くことになる。このことから最近では管を痛めるステンレスホースは使用せず、樹脂で被膜したホースを使用している。
排水管の更新方法には[1]切り替え工法(既存の位置と異なる場所に配管を更新する[2]取替え工法(既存管を撤去し、既存の位置に新管を配管する)[3]更生工法(既存の配管を既存の位置のまま、配管内面に樹脂等によりライニングまたはコーティングを施す)工法がある。どの工法選択には排水管の現状を調査し、長期的な視点での判断が必要となることから、専門の信用のおけるコンサルタントに委託することが良い。
排水管更新技術として、住まいながら施工の実現のため、短期間、低騒音、低振動、無粉塵で行える工法開発が行われている。
排水設備も給水設備と同様な理由から専有・共用一体的改修が望まれる。特に住戸内の横枝管に亜鉛鋼管(白ガス管)が使用されているマンションは居住者の使用状況に関わらず劣化が進んでいることが想定されることから、管理組合主導で改修を進めるべきである。
また、特に問題なのが専有の排水管が下階の天井に配管されている構造の集合住宅である。
排水立て管更新時にスラブ下排水管をスラブ上配管に変更することを計画することによりマンションの資産価値を向上させることができる。
そのためには長期優良住宅化リフォーム推進事業等公的助成制度の活用を検討することを提案したい。
以上 |