廤崌廧戭偺愝旛憶壒偺崲偭偨弌棃帠 |
暯惉25擭3寧1擔
姅幃夛幮僄乕丒傾乕儖丒僔乕僄儞僕僯傾儕儞僌 堦媺寶抸巑帠柋強 戙昞丂愇嫶 惓媊 |
|
愝旛憶壒偼丄堦斒揑偵壱摥帪偼掕忢憶壒偱偁傞応崌偑懡偄丅崱夞懳徾偲偟偨偺偼丄廧戭梡僄傾僐儞偺幒奜婡傗姺婥愝旛側偳偐傜敪惗偡傞掕忢揑側憶壒偵偮偄偰偺嬤椬憶壒偲搒忦椺偺乽憶壒婯惂婎弨乿偵偮偄偰丄嬤椬栤戣偲側偭偨帠椺傪傕偲偵曬崘偟傑偡丅
侾丏俀係帪娫姺婥
丂摿偵嵟嬤偱偼撪憰偵崌斅偦偺懠斅忬偵惉宍偝傟偨寶嵽傪巊梡偡傞寶暔偼丄婡夿幃姺婥愝旛偺愝抲偑媊柋晅偗傜傟偰偄傞丅捠徧乽俀係帪娫姺婥乿偲屇偽傟偰偄傞傕偺偱偁傞丅
丂婡夿姺婥偱偼丄戞嶰庬姺婥乮媼婥偼帺慠偵傛傝峴偄乮奐岥晹乯丄攔婥偼婡夿偵傛傝峴偆曽幃乯偑堦斒揑偱偁傞丅
丂婡夿姺婥愝旛偺梕検傪寛掕偡傞応崌偵偼丄僈僗愝旛偵昁梫側儗儞僕僼乕僪偺攔婥愝旛偼丄僈僗婡婍偺僈僗徚旓検偐傜嶼掕偟丄嫃幒偵偁偭偰偼婎杮揑偵偼侾恖摉偨傝帪娫摉偨傝俀侽m3偺怴慛嬻婥偺摫擖傪偟側偗傟偽側傜側偄偙偲偵側偭偰偄傞丅偝傜偵丄僔僢僋僴僂僗懳嶔偲偟偰廧屗慡懱傪姺婥懳徾偲偡傞応崌偵偼丄姺婥夞悢侽丏俆夞乛倛傪婎弨偲偟偰偄傞丅
丂彯丄嬊強姺婥愝旛偺懳徾偲側傞戜強丄梺幒丄愻柺強丄僩僀儗偼丄慡斒姺婥偲堎側傝丄昁偢偟傕忢帪壱摥偺昁梫偼側偔丄偦偺悈夢傝僗儁乕僗偺巊梡帪偵壱摥偱偒傟偽傛偄丅偙傟偵懳偟偰俀係帪娫姺婥偼丄梺幒摍偺姺婥憰抲傪慡幒姺婥偵巊梡偟丄忢帪壱摥偟偰偄側偗傟偽側傜側偄姺婥憰抲偱偁傞丅
俀丏姺婥愝旛偺峔惉
丂戙昞揑側姺婥峔惉椺偲偟偰丄僩儗僀丄愻柺強丄梺幒丄姺婥宯摑傪侾杮壔偟偰丄梺幒姺婥僟僋僩偵愙懕偟偰姺婥偡傞応崌丄姺婥検偼寶抸婎弨朄偵掕傔傜傟偰偄傞侾帪娫摉傝侽丏俆夞姺婥傪峴偆婎弨傪壓夞傜側偄傛偆偵搘傔側偗傟偽側傜側偄丅偝傜偵丄姺婥僟僋僩偺埑椡懝幐乮掞峈乯側偳傪峫椂偟偰丄姺婥検傪懡傔偵尒崬傫偱偍偔昁梫偑偁傞偨傔丄俀係帪娫忢帪姺婥検寁嶼傪奺廧屗柺愊枅偵嶼弌偟偰愝寁晽検傪枮懌偝偣傞偲僼傽儈儕乕僞僀僾廧屗偼丄堦斒揑偵侾俀侽m3乛倛偲側傞丅姺婥検偲偟偰偼丄嬊強姺婥偺戜強偺儗儞僕僼乕僪偺姺婥検偺侾乛俁掱搙偺儗儀儖偱偁傞丅
俁丏俀係帪娫姺婥丒忢帪壱摥帪偺敪惗憶壒
丂崱夞丄應掕挷嵏偡傞婡夛偺偁偭偨應掕帠椺偺寢壥傪帵偡丅
- 應掕傪峴偭偨儅儞僔儑儞偺梡搑抧堟偼丄戞侾庬拞崅憌廧嫃愱梡抧堟偱丄慜柺摴楬偼惗妶摴楬偺侾幵慄偱丄傎偲傫偳幵偺墲棃偼柍偄娬惷側廧戭抧偱偁傞丅姺婥愝旛憶壒偺塭嬁偺側偄僄儕傾偱偼丄奜晹憶壒偼係侽僨僔儀儖慜屻偱偁傞丅
- 奺廧屗偺俀係帪娫姺婥偺壱摥忬嫷傪屵慜侾侽丗侽侽乣屵屻俈丗侽侽傑偱偺侾侽帪娫偵搉傝俁侽暘娫娫妘偱壱摥揰専偟偨寢壥丄乽嫮乿壱摥俈俇亾丄乽庛乿壱摥俀侽亾丄乽掆巭乿係亾偺壱摥斾棪偱偁偭偨丅
- 儅儞僔儑儞偺奐曻楲壓庤悹傛傝6.3倣棧傟偨摴楬嫬奅慄忋丄崅偝4.5倣乮屗寶偰2奒憢憡摉乯偺應掕揰偺憶壒儗儀儖俆侾乣俆俀僨僔儀儖丄偝傜偵丄6.3倣偵摴楬暆6.1倣亖12.4倣棧傟偨摴楬斀懳懁偺摴楬嫬奅慄忋丄崅偝4.5倣偺應掕揰偺憶壒儗儀儖丗俆侽僨僔儀儖偑應掕偝傟偨丅
- 儅儞僔儑儞偺挿庤曽岦乮奐曻楲壓乯偵嬒摍偺挿偝偱俆揰暲楍偵應掕傪峴偭偨偑丄憶壒儗儀儖偺抣偼俆侽僨僔儀儖慜屻偲傎傏摨偠抣偱偁偭偨丅
- 姺婥愝旛壒尮偱偁傞奐曻楲壓撪偺忋晹姺婥僈儔儕偺捈嬤侾丏侽倣棧傟偵偍偗傞憶壒儗儀儖丗俇侽僨僔儀儖偱偁傞丅
係丏搒忦椺偵傛傞婯惂婎弨偲偺娭學
- 憶壒婯惂朄傗岞奞杊巭忦椺埲奜偵丄憶壒偵學傞乽娐嫬婎弨乿偲偄偆傕偺偑偁傞丅恖偺寬峃傪曐岇偟丄娐嫬傪曐慡偡傞忋偱堐帩偡傞偙偲偑朷傑偟偄婎弨傪掕傔偨傕偺偱偁傞丅乽娐嫬婎弨乿偼丄傕偲傕偲峴惌巤嶔偺払惉栚昗抣偲偟偰偺堄枴崌偄偱掕傔傜傟偰偄偨傕偺偑丄尰嵼偱偼嵸敾偺庴擡尷搙偺敾抐偱傕丄偙偺乽娐嫬婎弨抣乿偑嵦梡偝傟傞応崌偑懡偔尒傜傟傞丅
- 偙偺娐嫬婎弨傪摜傑偊偰丄奺搒摴晎導偱傕忦椺偱乽婯惂婎弨抣乿傪愝掕偟偰懳墳偟偰偄傞丅搶嫗搒偱偼丄暯惉侾俀擭侾俀寧俀俀擔晅忦椺俀侾俆崋乽搒柉偺寬峃偲埨慡傪妋曐偡傞娐嫬偵娭偡傞忦椺乿偱偼丄摿偵戞侾庬嬫堟丗戞侾庬丒戞俀庬掅憌廧嫃愱梡抧堟摍丄戞俀庬嬫堟乮戞侾庬丒戞俀庬拞崅憌廧嫃愱梡抧堟乯偵奩摉偡傞嬫堟偱偼丄壒尮偺懚偡傞晘抧偲椬抧偲偺嫬奅慄偵偍偗傞壒検傪婯惂偟偰偄傞丅戞侾庬嬫堟偱偼丄屵慜俉帪偐傜屵屻俈帪傑偱偼憶壒儗儀儖丗係俆僨僔儀儖埲壓丄屵慜俇帪偐傜屵慜俉帪傑偱偼係侽僨僔儀儖埲壓丄屵屻俈帪偐傜梻擔屵慜俇帪傑偱偼係侽僨僔儀儖埲壓偲愝掕偝傟偰偄傞丅戞俀庬嬫堟偱偼丄屵慜俉帪偐傜屵屻俈帪傑偱偼憶壒儗儀儖丗俆侽僨僔儀儖埲壓丄屵慜俇帪偐傜屵慜俉帪傑偱偼係俆僨僔儀儖埲壓丄屵屻俈帪偐傜梻擔屵慜俇帪傑偱偼係俆僨僔儀儖埲壓偺婯惂婎弨傪愝掕偟偰偄傞丅
- 婯惂婎弨抣偵帵偡傛偆偵丄憶壒偺壒検乮憶壒儗儀儖偺戝偒偝乯偱敾抐偡傞偙偲偐傜丄姺婥愝旛摍偺憶壒偼丄傕偲傕偲峴惌揑婯惂偵撻愼傓憶壒偱偁傞偙偲偑攚宨偵偁傞丅
- 挷嵏寢壥偐傜丄戞俀庬拞崅憌廧嫃愱梡抧堟偵奩摉偡傞嬫堟偱偁傞偙偲偐傜丄栭娫丒憗挬偺揱斃憶壒偑乽婯惂婎弨抣丗係俆僨僔儀儖乿傪俆僨僔儀儖挻偊偰偄傞偙偲偑妋擣偝傟偨丅
俆丏揱斃憶壒偺梊應曽朄
丂揱斃憶壒抐柺専摙恾偵婎偯偄偰幚應抣偺應掕揰偺埵抲偵偍偗傞揱斃壒偺梊應傪峴偆曽朄傪帵偡丅
丂乮壓恾偼僋儕僢僋偡傞偲丄戝偒偔偛棗偄偨偩偗傑偡丅僽儔僂僓偺乵栠傞乶儃僞儞偱摉儁乕僕傊偍栠傝偔偩偝偄丅乯
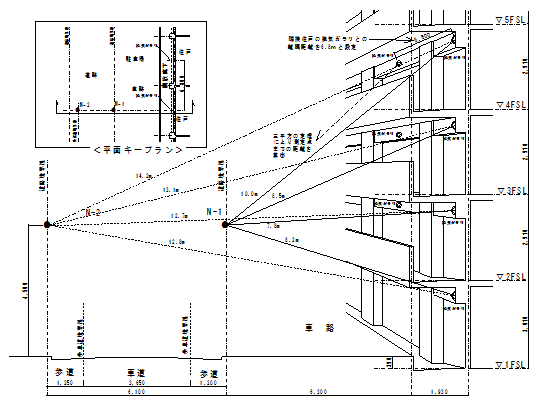
俆亅侾丏壒偺揱斃偲尭悐
丂壒偼壒尮偐傜墦偞偐傞偵廬偄彫偝偔側傞丅嫍棧偵傛傞尭悐検偼丄彫偝偄壒尮偼乽揰壒尮乿偲屇傃丄壒攇偼媴柺忋偵奼偑偭偰揱傢傞丅
丂姺婥僈儔儕偐傜敪惗偡傞憶壒偼丄敪惗尮偑僟僋僩偐傜敪惗偡傞壒偱偁傞偙偲偐傜丄揰壒尮揑尭悐傪偡傞丅嫍棧尭悐偺嶼弌偼揰壒尮偺棟榑幃傪梡偄傞丅
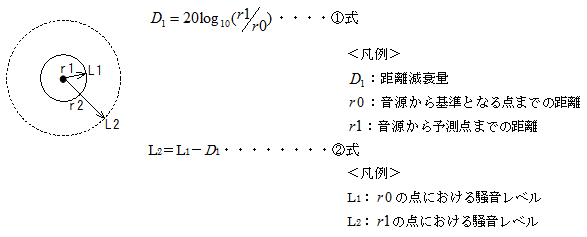
俆亅俀丏倓俛乮僨僔儀儖乯抣偺懌偟嶼
丂憶壒儗儀儖偼僄僱儖僊乕偦偺傕偺偱偼側偄偺偱丄偦偺傑傑扨弮偵壛偊傞偙偲偼偱偒側偄丅偦偺偨傔丄堦搙僄僱儖僊乕偵姺嶼偟偰壛偊丄嵞傃憶壒儗儀儖偵姺嶼偡傞丅
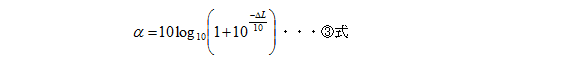
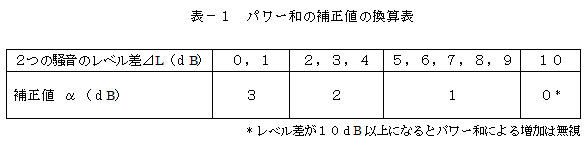
俇丏應掕寢壥
- 儅儞僔儑儞偺姺婥愝旛憶壒偼丄婘忋寁嶼梊應抣傪媮傔傞偨傔偺寁嶼偐傜媮傔偨姺婥僈儔儕丄廲丒墶丄俁廧屗亊俁廧屗亖俋廧屗偺敪惗憶壒偺僷儚乕榓偺寁嶼寢壥偼丄姺婥僈儔儕偐傜堦掕嫍棧偺抧揰偺揱斃憶壒儗儀儖偺幚應抣偺俆侽僨僔儀儖偲傎傏堦抳偡傞丅
- 傛偭偰丄慡廧屗偺姺婥愝旛偺敪惗憶壒偺僷儚乕榓偺寁嶼寢壥傕俋廧屗暘偺寁嶼寢壥傕傎傏摨偠抣偲側傝丄寶暔偐傜偺姺婥愝旛憶壒偼丄廲丒墶丄俁廧屗亊俁廧屗暘丄搒崌丄俋廧屗暘偺僷儚乕榓偺寁嶼偵偰梊應偱偒傞丅
- 俀係帪娫姺婥丒姺婥僈儔儕偺敪惗憶壒偺俇侽僨僔儀儖媦傃揱斃憶壒摿惈偐傜乽搒柉偺寬峃偲埨慡傪妋曐偡傞娐嫬偵娭偡傞忦椺乿乮暯惉侾俀擭侾俀寧俀俀擔丂忦椺戞俀侾俆崋乯偺擔忢惗妶摍偵揔梡偡傞婯惂婎弨偵掞怗偡傞応崌偑憐掕偝傟傞偙偲偐傜丄愝寁忋偺拲堄偑昁梫偱偁傞丅摿偵丄戞侾庬嬫堟丄戞俀庬嬫堟偵寶愝梊掕偺廤崌廧戭偼梫拲堄両
俈丏帠屻偺懳嶔偲偟偰峫偊傜傟傞姺婥曽嶔偲栤戣揰
- 俀係帪娫姺婥偼丄慡屗丒忢帪壱摥偺愝旛偱偁傞偨傔丄戞俀庬嬫堟偱偼俆僨僔儀儖掅尭偝偣偰栭娫偺婯惂婎弨抣傪枮懌偝偣傞偨傔偵偼丄儔儞僟儉偵慡屗悢偺俁俆亾埲壓偺俀係帪娫姺婥愝旛壱摥偵惂尷偟側偗傟偽側傜側偄丅傛偭偰丄尰幚揑偱偼側偄丅
- 姺婥検傪敿暘偵壓偘偰丄侾俀侽m3乛倛傪俉侽m3乛倛偵愝掕愗傝懼偊偰傕丄俀乣俁僨僔儀儖偺掅尭検偟偐婜懸偱偒側偄丅傑偨丄梫媮姺婥検傪枮懌偡傞偙偲偑弌棃側偄丅
- 姺婥僈儔儕偺僟僋僩僩僢僾偵杊壒僇僶乕傪愝抲偡傞丅姺婥愝旛憶壒偺戩墇廃攇悢偑侾倠Hz懷偵偁傞偙偲偐傜丄俆僨僔儀儖偺掅尭検偼壜擻偱偁傞丅偟偐偟丄杊壒僇僶乕偵傛傝晽検偺棳傟偑壓岦偒偲側傝丄姺婥僟僋僩偺埑椡懝幐偺塭嬁偑峫偊傜傟傞丅尰応偵偰妋擣偡傞昁梫偑偁傞丅
亙嶲峫暥專亜 |
|
|
丂寶抸暔偺幷壒惈擻婎弨偲愝寁巜恓丂戞擇斉 |
擔杮寶抸妛夛曇 |
媄曬摪弌斉 |
丂嬤強偑偆傞偝偄両憶壒僩儔僽儖偺嫲晐 |
嫶杮揟媣挊 |
KK儀僗僩僙儔乕僘 |
| |
乮敧屗岺嬈戝妛丂戝妛堾嫵庼乯 |
|