マンション設備に関する標準管理規約の落とし穴
~その工事、専有部分が含まれていませんか?!~ |
平成30年2月1日
戸部マネジメントオフィス 代表 戸部 素尚 |
|
1.はじめに
分譲マンションは、外観上は1つの建物ですが、法律上共用部分と専有部分と大きく2つに分かれています。これは単なる民法上の共有関係だけでは解決できないとする共同住宅としての合理的な考え方によるものです。
建築工事であれば、境界線はここまで、とすることが明確に可能ですが、こと設備となると突然難易度が上がり、非常に線引きが難しい課題になってしまいます。今回は、設備を改修するうえでの管理規約上の注意点をお知らせしたいと思います。もしかしたら、知らず知らずのうちに、管理規約違反になっているかもしれません。
2.専有部分に影響する設備とその管理規約の変更案
大きくは、給水管、排水管、ガス管、電気配線、通信配線、TV共視聴設備、消防設備、オートロック設備が挙げられます。それぞれについて、どこまでが専有部分で、どこまでが共用部分なのか標準管理規約ではどのように記載されているかを確認してみましょう。
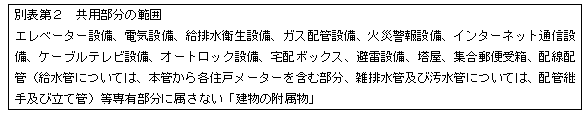
給水管にあっては「本管から各住戸メーターを含む部分」とあり、排水管にあっては「雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管」とあり、その他電気や消防設備については一切触れられていません。そこで、第7条を見てみましょう。
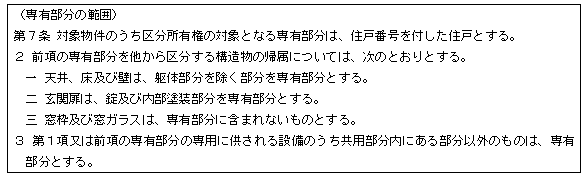
第3項に「設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする」とありますね。つまり、別表第2に書かれていない設備のうち、「共用部分外にあるものは専有部分だ」ということです。意味は分かりづらいので、具体的に見てみましょう。
(1)電気配線
電気配線の場合には、室内に入る前に共用幹線より接続された電気メーターがあります。余談ですが、電気メーターは共用部分でもなく、電力会社のもちものですから、管理組合の共用部分ではありません。管理対象物からは除外されます。
電気メーターから内側となるわけですが、「共用部分内にある部分」とはいったいどこを指すのか?ということは具体的には書かれていません。したがって、常識的かつ一般的に考慮すると、室内の電気の配線は次のような流れになります。
①電気メーター
②住戸内分電盤
③各コンセント・電気機器(照明やエアコン等)
②~③の配線については、専有部分内にありますので、専有部分で異論はないでしょう。
しかし、①~②については?一部、電線管がコンクリートの中を通っており、室内に飛び出ています。これを標準管理規約に当てはめてみると「コンクリート内の配線は共用部分」「専有部分配線は室内に出ているところから」ということになります。ただし、配線は途中で途切れているとか接続されているわけではないし、ここだけ専用使用権を当てはめるのも厄介なので、通常は専有部分としています。したがって、以下の通りとなります。
【Ⅰ 厳密に考慮した場合の電気配線】
電気配線については、専有部分である室内側空間に存する電気配線のみを専有部分とし、それ以外の部分については共用部分とする(ただし電気メーターを除く)。
【Ⅱ 合理的に考慮した場合の電気配線】
電気配線については、電気メーターより室内側二次側を専有部分とし、それ以外の部分を共用部分とする。
※メーターがどうのというのは、水道メーターと同じで、暗黙の了解かつ常識的なものとして当然に除外され得ます。
工事の際には、どの考え方でいくかを明確にして着手できるようにすると望ましいでしょう。
電気配線と同じく、ガス管においてもメーターはガス会社のもちものであり、そこから二次側が専有部分とすることが望ましいと言えます。
(2)通信配線(電話・インターネット)(≒弱電設備)、TV共視聴設備
通信配線とTV共視聴設備は、いずれも異なる設備ですが、端子があり、個別の機器と接続するという意味では同じですので、ここでは同じように取り扱います。
既述の通り、別表第2には何も書いてありませんので、「設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする」というのが適用されます。しかし、電気配線等と大きく異なるのは、メーターがないことです。メーターがないのであれば、どこで区切るべきでしょうか?回答としては2通りであると考えられます。
【Ⅰ標準管理規約に従った場合】
通信配線及びTV共視聴配線については、専有部分である室内側空間に存する配線並びに端子のみを専有部分とし、それ以外の部分については共用部分とする。
【Ⅱ合理的な解釈によった場合】
通信設備配線及びTV共視聴設備については、各戸に設置された端子を含む部分までを共用部分とする。
※管理規約の変更が必要です。
標準管理規約に従った場合には、特にTV映りが悪いといった事案の場合、どこで原因が発生しているのか、非常にわかりづらいということがあります。また、古いマンションによっては、専有部分を経由して隣戸へ接続されていることもあります。そういった場合、「専有部分」ということは処分権までも与えてしまうことになりますから、室内にある設備は「私はTVを見ないから、TV配線はすべて撤去してしまう」決定ができてしまいます。そうすると、隣戸への接続が途切れ、電波の下流住戸に影響を及ぼすことから、実際にはこのような標準管理規約に従った運用は無理があると言えます。さらに、TV配線は電線管等で配線されているよりも、PSやMB等で最後に壁を這うように上下に配線されていることも多く、上下階のための共用の配線でありながら、室内空間にあるものは専有部分であるということについて考慮してみても、無理があると言えます。他方、端子までを共用部分とする必要があるかどうかについても、TVは電波を分け合って受信しているため、ある住戸が室内に端子をたくさん増やしてしまったせいで電波の下流住戸に十分な電波がいきわたらないというおそれもあるからです。
ただ電話配線においては、共用部分であるMDFより各戸へ行っていますが、これも専有部分としてしまうと躯体内部の配線専用管のスペースを利用しているため、各戸が自由に新規に光配線等をされると結果として配線専用管が満杯となり、先に実行した方のみがその利益を享受でき、そのあとの人は利益を享受できないという不公平な結果にもなります。
このような結果から、通信配線やTV配線については、端子までを共用部分とすることが最も合理的であると言えます。
(3)消防設備
専有部分に影響のある消防設備のうち、自動火災報知設備、スプリンクラー設備が挙げられます。これらは消防法によって設置を義務付けられていることから、専有部分内にあるからと言って勝手な撤去は許されないと考えられます。しかし、標準管理規約では、通信配線と同じく、やはり解釈が異なってしまいます。
【Ⅰ標準管理規約に従った場合】
消防設備については、専有部分である室内側空間に存する配線(配管)並びに感知器(スプリンクラーヘッド)のみを専有部分とし、それ以外の部分については共用部分とする。
【Ⅱ合理的な解釈・法令に従った場合】
消防設備のうち、自動火災報知設備にあってはその配線、感知器を含む部分を共用部分とする。
消防設備のうち、スプリンクラー設備にあってはその配管、スプリンクラーヘッドを含む部分を共用部分とする。
と、こうなります。法令上撤去が禁止されていることからも、Ⅰの標準管理規約に従った運用ではまずいことがよくわかります。以上からも、消防設備に関しては管理規約を変更して運用すべきと考えられます。
(4)オートロック設備
オートロック設備は非常に複雑でわかりづらいものとなっています。
各戸の住宅情報盤から自動ドアの開錠装置までの配線、各戸別インターホンとの接続は当然としても、管理室の住宅情報盤との接続、場合によっては消防設備との接続や玄関前の防犯ベル又はガス検知器、警報装置、果ては警備会社に自動的に連絡されるような接続方法もあります。
こればかりは一般的な文言はありませんが、共用部分とすべき部分と、専有部分とすべき部分とでは明確に分けやすいので、以下提案してみます。
【Ⅰ標準管理規約に従った場合】
オートロック設備については、専有部分である室内側空間に存する配線並びに住宅情報盤のみを専有部分とし、それ以外の部分については共用部分とする。
【Ⅱ合理的な解釈によった場合】
オートロック設備については、共用廊下に設置された戸別ドアホン及び住宅情報盤並びにそれらを結ぶ配線を含む部分を専有部分とし、住宅情報盤より管理事務所その他共用部分に設置された設備に接続するまでの配線並びに住宅情報盤本体を共用部分とする。
標準管理規約に従うと、住宅情報盤が専有部分になってしまいます。これでは、例えば消防設備と接続していた場合、実際にあった事例として「端末断線表示」が常に出されることとなり、管理室で警報が鳴り響いてしまいます。したがって、オートロック設備についても実際の運用や接続をよく確認して管理規約を変更することが望ましいでしょう。
3.最後に・・・
標準管理規約自体は参考資料としては優秀ですが、「標準管理規約をそのままご自分のマンションに持ってくること」がいかに脆弱かつ危険なものかお分かりいただけたかと思います。
本当は設備以外にも、建築的なところでも明確に境界線を定めたほうがいいものもありますが、次回のコラムにしたいと思います。
以前にも記載しましたが、マンションは二つとして同じ居住者、同じ建物、同じ立地のものがありません。住まい方も歴史もすべて異なりますから、どのような運用が良いのか、まずはマンションの設備がどうなっているのかを理解し、マンションごとによく話し合い、結論を出していければと願うばかりです。そうすることによって、今年と昨年とで運用が違う!などということが発生しなくなります。
また、これからマンション管理士試験を受けるであるとか、マンション管理士として開業をしようとする方にあっては、ぜひ設備等の知識・見識を持って管理規約の改定に当たっていただきたいと願っています。
|