|
■はじめに
これまで給水管リニューアルでは、給水システムの変更により貯水槽を廃止してフレッシュな給水と敷地の有効活用、そして給水設備にかかるランニングコストを低減するための工事が盛んに行われてきたが、これもほぼ一巡した感がある。
最近では、使用配管材料の耐用年数の違いや用途の違いもあり、給水管リニューアルに続いて排水管リニューアルに注目が集まり、更新工事・再生工事・ライニング工事などで様々な工法がリリースされ活発に行われている。
しかし、現在の我々施工会社を取り巻く環境は、『作業員不足』、『更新工事による長期間の入室作業』、『将来の改修を考えていない建物』などにより、現場環境は厳しい状況が続いている。
■現状の問題点
我々がリニューアル工事を行う集合住宅は、そのほとんどが築30年程度経過したものである。30年経過した建物では、室内に設置された共用部排水管の改修工事が多く、道連れ工事で内装の解体復旧があり、室内に作業員が入るならば、ついでに専有部給水給湯管の更新工事も同時に実施するケースが多い。ここで問題となるのが長期間の入室作業だ。
下記は、弊社で施工した共用部排水管更新、専有部給水・給湯管更新工事の入室作業工程だが、全てを同時に一斉に改修しようとすると1部屋当たり6日間の入室作業となった。
(下図はクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
<あるマンションの共用部排水管、専有部給水・給湯管更新工事の入室作業スケジュール> 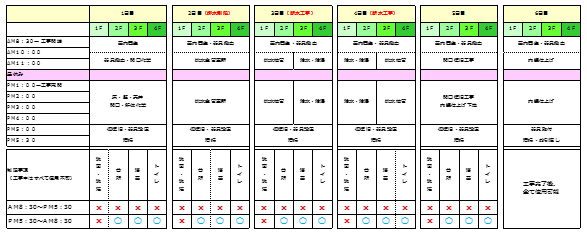
この6日間工程は、話の筋書き(共用部排水管更新工事と道連れ工事と専有部給水給湯管更新)から見ると非常に合理的と思われがちだが、実は居住者にとっても工事会社にとっても非常にストレスのかかる工事であり、不合理であると最近になって感じることが多くなった。それは、居住者からの意見や作業員不足によるものである。
■給排水管リニューアルの課題
1)専有部入室作業について
今回の工事で徹底的に改修します。と宣言して開始した入室作業を伴う改修工事では、工事後のアンケートでは、
- 合理的に改修するという意味は理解できるが、連続6日間工事は耐え難い
- 主婦にとって毎日毎日、作業員が入ってくる環境は苦しかった
- 連続工事ならせめて3日間にしてほしい
- 職人さんが大勢で入室してくるから不安だった
などのご意見をいただくことが多くなった。もしかしたら、1回の工事で徹底的に改修するというのは、こちら側のエゴであって、お客様は共用部の排水管更新工事の後、数年後に専有部給水・給湯管更新工事の実施を望んでいるのかもしれない。我々にとっても数年後の工事がリピートで見込めることができたら有難いことでもある。今後は、このあたりの配慮を念頭に置く必要があるのかもしれない。
2)作業員不足について
建設労働者の減少や高齢化、東京オリンピックの影響もあり、作業員がまったく足りていない状況が続いている。特に我々のような一般人や主婦の目線の中で作業を行わなくてならない、紳士的で子供や高齢者にもひとりひとりに挨拶のできる、きれいな作業着を着用した専有部の作業が得意な作業員が不足している。そして、専有部の工事では、配管だけではなく内装解体や下地工事などの多能工が求められている。
我々の改修工事では、作業員に要求するレベルが高い割には、労務費は仮囲いの中で行われている新築工事と大差がない。それでは、作業環境の厳しい改修工事へは優秀な作業員はますます入ってくることはない。今後は、労務費だけではなく、残業や休暇などを含めた労働環境でも新築工事との差別化を図り、優秀な作業員を確保していくことが必須である。
また、業界全体で若い人を確保して、教育し、成長させて、定着させていく仕組みづくりを本気で取り組む必要があると考える。
3)リニューアル現場での女性の活躍に期待
入室作業では、主婦の目線の中で作業を行うため、女性感覚での現場運営が居住者から評価される。近年では、女性の作業員のほか、女性の現場監督を配置する企業も増えてきた。弊社でも平成20年2月より『幼い子供を持つ主婦』を現場巡回に採用し、主婦目線での現場運営に注力してきた。平成27年8月には日本経済新聞にも掲載され、世間の女性現場監督への期待が伺える。これからの給排水管リニューアル現場では、主婦の目線だけではなく、高齢者が居住する中での入室作業も増加していくので、入室作業前のお片付けや工事内容説明など、居住者に寄り添ったサービスでリニューアル現場で活躍する女性に期待したい。
そして新築工事との徹底した差別化を図り、リニューアル産業の健全な発展を夢見るところである。
(下図はクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)

|