排水立て管の更新性向上のための技術開発
|
平成22年1月1日
株式会社 長谷工コーポレーション 山鹿 英雄 |
|
新政権が発足して100日が経過したにもかかわらず政権交代の不安定感がいまだ続いており、昨年9月のリーマンショックからの立ち直りの兆しさえ見えない世相でありますが、住宅エコポイントの創設や自然エネルギー利用の評価制度により、住宅関連の市場の活性化が待ち望まれるところです。
今回はわれわれの業務に関係する排水配管の更新技術に関して記載します。
福田政権時「200年住宅構想」が発表され、孫世代まで住み続けられる住宅を作り、今までのスクラップ&ビルドから維持メンテナンスを続けながら永く住み続けられる住宅を目指す社会作りに転換をし始めています。
その中で、「長期優良住宅」制度が発足し、戸建住宅を中心に普及が始まっています。
先日、新聞でも取り上げられていましたが、この制度を利用した住宅は、戸建住宅では2万4000戸を超え新築住宅の2割まで浸透しているにもかかわらず、マンションでは全国でわずか5棟だけの採用であることが報じられていました。
その主な原因として、新聞記事では長期優良住宅の認定基準で求める耐震等級レベルを守るためのコスト増があると紹介されていましたが、その他、維持管理等級-3が求める専用部分に入ることなく、維持管理ができる排水立て管の設置が条件となっていることも採用が少ない理由のひとつだと思います。
現状の長期優良住宅の認定条件では、排水立て管の室内設置はある条件を満たさない限り認められず、住戸フレーム外のメーターボックスや光庭のボイド空間内に設置する必要があります。
その場合の配管工法として、SI住宅で取り入れられている「緩勾配配管工法」の適用が考えられ、衛生器具から専用管で立て管に接続された排水ヘッダー迄配管する「排水ヘッダー方式」が採用されています。(排水ヘッダー接続口には各系統別の掃除口を設け、接続衛生器具名とトラップまでの配管距離を表示し、戸外から清掃できるよう配慮されている。)
排水ヘッダー方式の場合、配管距離が通常の配管と異なり、緩勾配でありしかも配管距離が長いため定期的な配管洗浄は必至であると考えます。
その場合の配管洗浄方式は高圧洗浄方式を採用することになりますが、住戸内に入ることなく排水ヘッダーから作業を行うことができる利点がありますが、清掃時のトラップからの吹き上げや封水切れ等の防止のため立ち入る必要があります。
マンションの排水管洗浄会社は排水横引き管清掃だけでなく、各衛生器具の排水トラップの清掃までの業務委託を受けています。そのためSI住宅の場合であってもメンテナンス時は室内作業が伴なうことになります。
又、排水立て管の洗浄については、専用枝管と立て管を同時に清掃するラップ洗浄方式を採用している場合が多く、排水立て管掃除口を使用して清掃することは特殊なケースであると聞いております。
よって、排水管を維持管理する上では、SI住宅も従来型住宅でも変わりはないと考えます。
一方、排水立て管は、排水ヘッダー方式であっても配管寿命があり、比較的長寿命であるといわれている排水鋳鉄管でも30~40年程度であると言われています。
最近の知見では、配管内のスライムの微生物腐食による配管腐食や定期メンテナンスに伴なう高圧洗浄ステンレスワイヤーメッシュホースによる洗浄痕からの漏水が問題となっています。いずれの場合も配管更新は長期修繕計画に組みいれなくてはいけない重要なテーマです。
排水立て管を施工する場合、我が国の排水管接合は、片受けタイプの接合方法をとる場合が多く、各階床で完全固定(穴埋め)されている排水立て管を更新する場合、配管切断と床ハツリを行うことにより配管を取り除く必要があり、排水立て管の更新を阻害する大きな要因となっています。
欧米で多く用いられている突合せジョイント(NO-HUB継手)下図参照の改良を行い、床穴埋めを取り外し可能な耐火部材を開発することにより、配管更新性を高めることが可能であると考えます。
同時に、室内排水立て管の更新工事にともなうインフィル(造作工事)の道づれ工事を要しない工法開発を行うことも必要です。
これらの技術開発を行うことにより室内造作を壊すことなく短時間で配管更新が可能となり、長期優良住宅の維持管理要件を満たすことが可能となるのではないでしょうか。
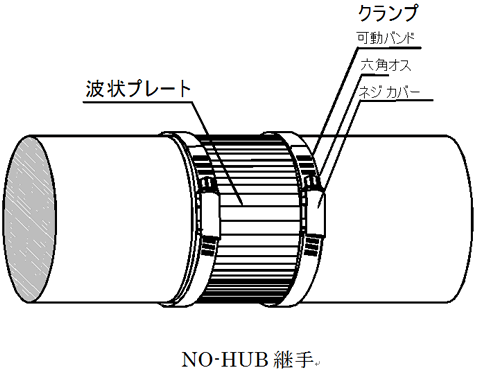
(画像をクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
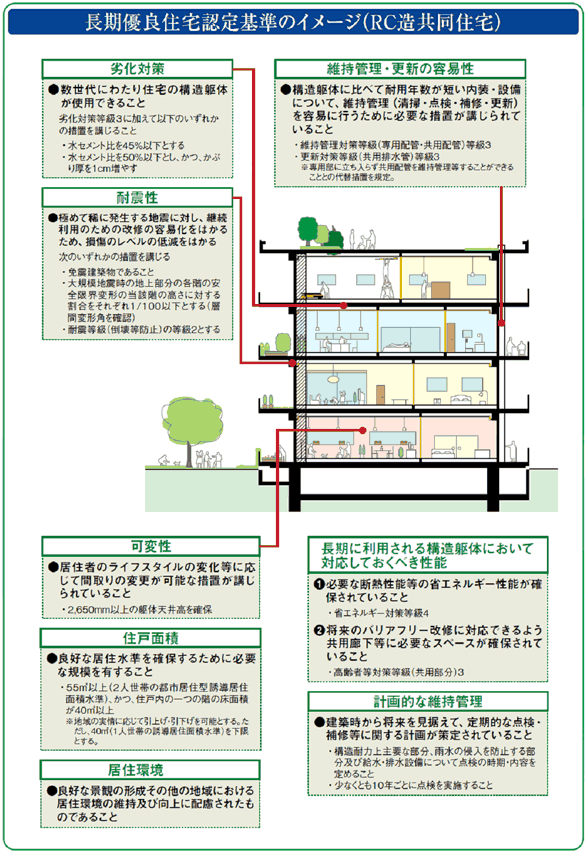
参考資料:長谷工コーポレーション
以上 |