|
1.はじめに
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 「住宅相談と紛争処理の状況」2009年6月の2008年度の共同住宅に関する相談内容を観ると、「遮音不良」や「床鳴り」「異常音等」の音に関連する不具合の相談が多いことが分かる。
不具合部位では、「床」「内壁」「外壁」の不具合が多い。不具合事象と関連して、上下階や隣戸等からの騒音等が問題になっていることが考えられる。
この音に関する不具合において、今回、「設備機器」や「排水配管」「給水・給湯配管」「浴室」に関連した騒音問題の中から、「排水配管、排水設備機器」に絞って、その代表的なクレーム事例をもとに設備系騒音問題について紹介させて頂きます。
(画像をクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
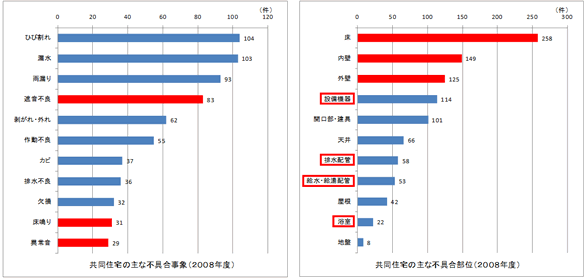
2.日常生活に伴う発生音
共同住宅特有の住宅の音環境において、発生しやすい不具合は、床衝撃系の騒音が多く、床・壁・給排水管等の固体を媒介して伝わるものが多い。
建築系では扉、窓、室内建具や引戸、襖の開閉時に発生する衝撃音によるものが多い。最近では、台所のカウンター、吊り戸棚の開き戸、引き出しの開閉音などの固体音が建築音響障害として問題となり、引き出しに衝撃音緩和対策(ソフトクローズ機能)が施された製品も標準装備されつつある。
設備系では、トイレの行為音、排水音、給水栓器具使用に伴う発生音(ウォーターハンマー)、風呂場の洗い場行為音、ディスポーザーのモーター音などが問題となることがある。
3.設備配管・機器による騒音問題
3-1.排水管からの排水音
<エントランス直上階住戸、排水竪管の横引き配管による騒音事例>
| □ |
2階住戸スラブ下に排水竪管の横引配管が集中し、各居室で排水音が断続的に発生する。排水竪管から横引配管に排水が流れると、室内暗騒音レベル22dBAから27dBAに音が大きくなる。 |
(画像をクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
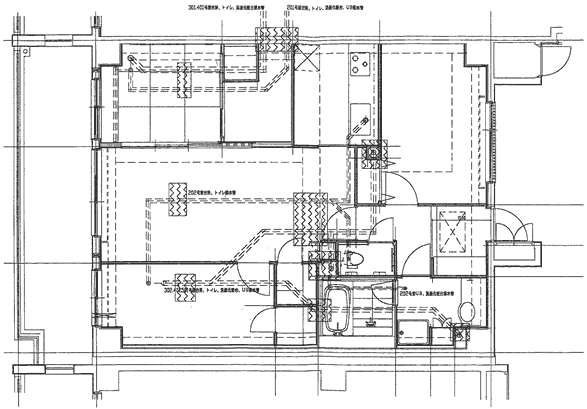
2階 エントランス直上階住戸 平面及びエントランス天井内横引き排水配管図
| |
3階
トイレ排水時
音源側(トイレ内) |
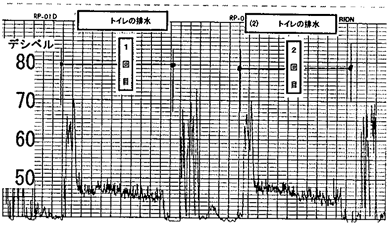 |
| |
2階
バルコニー側洋室 |
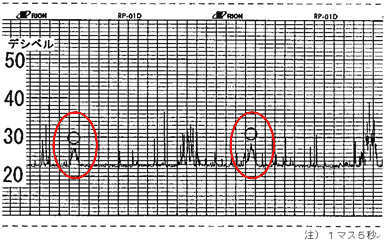 |
3-2.排水管の熱収縮による衝撃音
<冬季における排水管の熱収縮に伴う衝撃音発生事例>
| □ |
1階住戸にて「ドン」や「ズー」という音が断続的に聞こえる。 |
(画像をクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
 |
直下の地下ピット内
排水管の状況 |
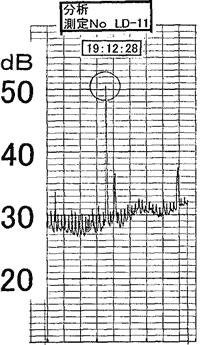 |
衝撃音発生時のレベル記録
約50dBが観測された。 |
3-3.排水ポンプ稼働音
<雨水貯留槽の排水ポンプ稼働音発生事例>
| □ |
2階住戸にて、降雨に伴う排水ポンプ稼働時のポンプ音が聞こえる。 |
(画像をクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
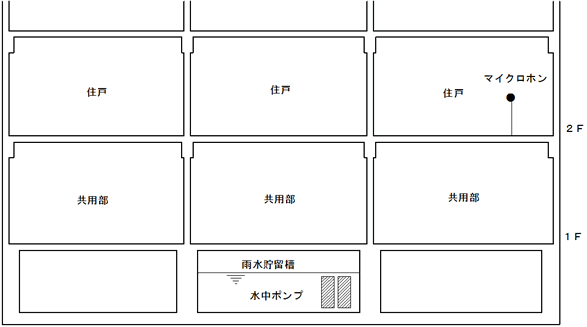
雨水貯留槽及び、騒音計設置略図
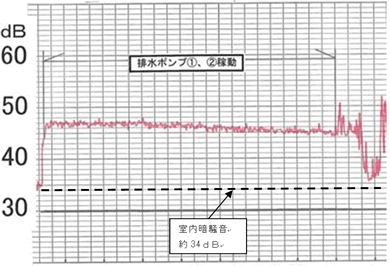 |
排水ポンプ稼働時における
2階居室の騒音レベル記録
34dBA → 47dBに上昇 |
4.給排水設備騒音に対する設計目標値とその対策
4-1.日本建築学会の給排水設備騒音に対する設計指針*1
| □ |
専用部の住戸内騒音 ・・・ |
集合住宅の隣戸、上下階の各室の組合せにおいて、要求される室内騒音に対する基準 |
| |
他住戸の「便所」「浴室」「洗面所」「台所」から発生する給排水騒音は、35dBA以下を推奨基準としている。 |
| □ |
共用部から各住戸内への騒音・・ |
「EV」「ポンプ室」「電気室」「機械式駐車装置」等の共用設備機器から発生する設備騒音は、専用部の室内騒音に対する基準よりさらに5dB 低い、30dBA以下とすることが必要とされている。 |
| |
*1)「建築物の遮音性能基準と設計指針」 第二版 日本建築学会編 技報堂出版より抜粋 |
4-2.設備騒音における音の特性と不快感
| □ |
集合住宅における音の問題は、音の大きさを表す騒音レベルの問題ではなく、"聞こえる"ことが問題になる。 |
| [1] |
聞こえる音の特性 |
| |
音を取り扱う場合、音の強さと音の大きさを明確に区別する。音の強さというのは、音の物理的な量のことであり、音の大きさというのは、音を耳で聴いて感じる感覚量のことである。よって音は、感覚的に個人差があり、気になり出すと、聞こえることが問題として大きく提起される。 |
| [2] |
音の不快感 |
| |
音の不快感は、音の強さと周波数によって決まる。例えば、高い音は低い音よりうるさく感じる。さらに、純音は、さまざまな周波数成分を多く含む音よりうるさく感じる。 |
| [3] |
音の問題へのアプローチ |
| |
聞こえることが問題となる、さほど大きくない音が問題視されるのは、閑静な郊外に立地するマンションに多い。都市部では環境騒音(道路騒音)の影響が大きいので、ほとんどマスキングされて、聞こえることが少ないので問題になることがない。
さほど大きくない音でも、音の特性、音の不快感を充分理解して、感覚的、心理的に気にならないようにすることが対策の基本対応として必要とされる。 |
|