|
1.現状のマンションにおける設備配管の検査機器、調査方法、調査機器について
1-1 非破壊検査
1)内視鏡(ファイバ-スコ-プ)調査
挿入部(対物部)、接眼部、操作部、ライトガイド部から構成され、配管内部に挿入しライトガイド部より照明光を入光し配管内の腐食、劣化状態を観察します。配管内の錆瘤の発達状況等の腐食・劣化、堆積物・付着物状況、つまり等を目視し、写真・ビデオ等の撮影装置に接続し記録することが出来る。
配管内部を観察できるため、もっとも頻度が多く、水栓器具を取り外した配管、掃除口、排水口から挿入する。形状として外径φ4.5mm以上、長さ3m程度のものが比較的多く使用されており、給水管20Aの場合で2~3箇所程度のエルボを観察することが可能。排水管50Aの場合でも2~3箇所程度のエルボを通過し観察することが可能。
また、挿入部が長く、管口径の比較的大きい配管(屋外埋設排水管、室内共用立管等)には押込みタイプの管内検査CCDカメラ(挿入長さ 30m程度)を使用し管内を観察する。(腐食にともなう減肉状況を数値で表すことは出来ない)
(画像をクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
2)超音波肉厚測定調査
配管に人間の耳では聞くことの出来ない高い周波数(超音波)を入れ、鋼内部を伝わり裏面で反射された超音波を電気エネルギ-に変換し、往復の伝播時間を厚さ換算し表示します。
配管の表面にプロ-ブ(探触子)を直接あて、腐食・劣化による配管の減肉状況を実測し残っている管の肉厚を知ることができる。
機器の分解能としては、±0.1mmまで表示し、測定範囲は1~10mm程度のものが比較的多く使用されている。
配管口径100Aで測定点数100、口径200Aで測定点数200程度測定し配管の推定残存寿命を診断することが可能。(配管の用途、種類によっては不向きな場合がある)
(画像をクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
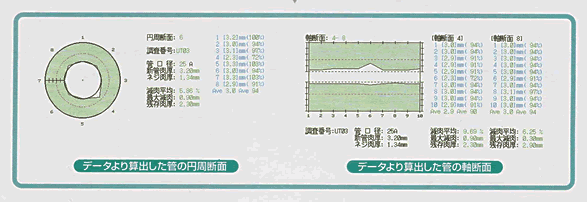
3)エックス線調査
エックス線は、電磁波と呼ばれる波の一種で物体を透過し、白黒フィルムを感光させる作用があり、人のエックス線撮影と同様に配管の後ろにフィルムを置きエックス線を照射します。
透過の度合いによって、フィルム上に白黒濃淡の影像を感光しフィルム上の可視像をを観察します。濃淡により減肉状況を知ることが可能。場合によっては、モニター管(対象配管と同じ材質、同じ形状、同じ形状の階調管となっており、その最大肉厚部は対象配管と同じ肉厚になっている)を並べてより正確な減肉状況を把握し、配管の推定寿命を診断することが可能。
また、近年配管の更新工事において床、壁等に配管を通すため貫通部にエックス線を照射し、鉄筋の位置、電気配線の位置等を確認するために使用することが増えている。
エックス線撮影時は、立ち入り禁止区域を設け、区域内に立ち入らないよう十分注意が必要である。
(画像をクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
1-2 破壊検査
1)サンプリング管調査
最も多い調査で抜管調査とも言われ配管の一部を抜取り管を半割りに内面の腐食状況を観察する。現状の劣化状況が確認でき、配管の種類、用途に限定されず、腐食・減肉状況、残存肉厚等が明確に判定可能。劣化している箇所の配管を抜き取るため配管工事にともなう2次的な被害(錆つまり、漏水等)が発生する可能性が高いため充分注意する必要がある。
(画像をクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
2.調査方法、調査機器の短所、長所について
(表の画像をクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)
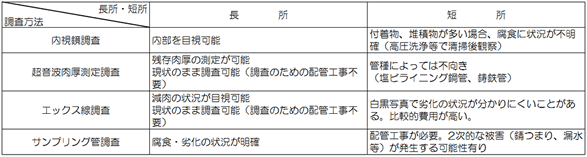
3.まとめ
設備配管の劣化調査については、図面、改修履歴等で充分な検討を行い、さらに一次診断の目視調査をもとに、建物の現状を考慮し調査方法、調査機器等を選定するすることが望ましい。
|