|
マンションの給水系統には各種用途に合わせて多くの給水用自動弁が使用されており、その使用目的・トラブル等をご紹介します。
現在、給水用に使用される自動弁は平成9年厚生省令14号に基づく性能基準に適合した製品であり、また、平成9年10月以前は(社)日本水道協会型式登録品が使用されています。
1.受水槽(高置水槽)まわり:
1)定水位弁:受水槽は配水管断水時に建物内の水が配水管への逆流を防止します。定水位弁は受水槽の水位を一定に保持し、短時間の断水等でも安定した給水を確保します。スケールによる固着やボールタップへの配管目詰まりによって、オーバフローや断水等が発生します。
2)緊急遮断弁:大地震時に水槽内の水を保持し、地震後の給水機能を確保します。水槽入口側への設置は地震後の赤水など汚れた水の流入を防止、出口側への設置は貯水確保と配管の破損による漏水等の二次災害を防止します。
万一への対応が使用目的であり、遮断弁・感震器・制御盤バッテリーの機能を定期的に確認する維持管理が重要です。
2.給水本管:
1)ゾーニング用減圧弁:高層建物における低層階等、系統別の適正圧力による給水によって、給水栓・洗浄弁の必要圧力保持、ウォータハンマーや騒音の低減などの機能があります。
ディスクの凹みや損傷による二次側圧力の上昇、減圧弁や水栓よりの騒音などがあります。
2)空気抜弁:給水管頂部に設置して、水に溶存する空気が分離し発生した空気を排出し、給水圧力の脈動や配管部材の腐食を防止します。
ディスクへのゴミ噛みによる外部漏洩(排水管へ放出)やシート部の詰りによって居室内の水栓より水と空気が排出する水はね現象などが発生します。
吸排気弁:空気抜弁の機能、初期通水時の急速排気機能と負圧発生時の急速吸気機能があり、給水縦管で負圧が発生した際に、逆サイフォンを解消し居室内から給水管への逆流を防止し安全な給水を確保します。
東京都の増圧直結方式・直圧直結方式には、吸排気弁の設置が義務付けられています。
3.メータボックスまわり:
1)戸別給水用減圧弁:ゾーニング減圧と異なりメンテナンス時は各戸で対応ができ、節水、水栓からの騒音低減などの効果があります。
スケール等による摺動不良によって減圧不良による水はねやウォータハンマーの発生、騒音の発生などがあります。
2)単式逆止弁:断水時等に居室内の水が給水本管へ逆流することを防止します。
逆止弁も給水の安全性を確保する目的であり、維持管理が重要です。
3)メータユニット:止水栓・戸別給水用減圧弁・逆止弁・台座を一体化したもので、メータボックス内での施工性やメータ更新時の交換などが容易になります。
3.居室内:
1)水撃防止器:シングルレバー水栓の開閉、シャワー水栓の切換え等によって発生するウォータハンマー(騒音)を吸収します。
ウォータハンマーによる騒音は壁や給湯器など思わぬ場所で発生しますが、防止器は水撃を発生させる水栓の直近に設置することで効果があります。
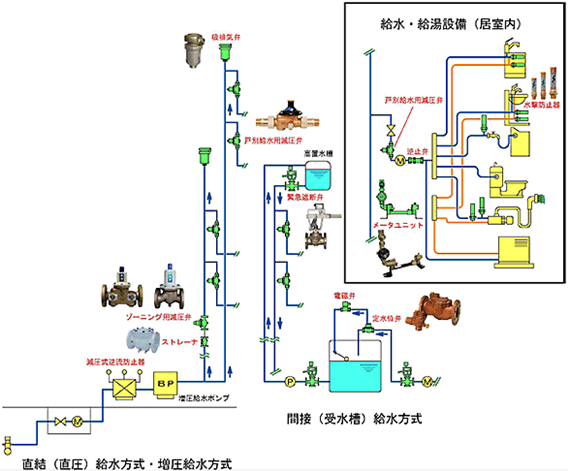
4.その他:
1)マンションの給水設備では紹介した品目以外にも、ポンプ周りには一次圧力調整弁やストレーナ、給水本管の水撃防止器やゾーニング減圧弁にはバイパス機構内蔵減圧弁、戸別給水用には各戸の最大流量を規制する減圧定流量弁、電気温水器用等の水道用減圧弁・温水器用逃し弁、また、散水栓等に使用するバキュームブレーカなど用途に応じて各種の自動弁があります。
5.保守点検:
給水に使用する自動弁の本体・要部などの接液部は、青銅・ステンレスなど錆びない材料を使用しています。また、駆動用のダイヤフラム、弁体部のディスク、シール部のOリングなどゴム部材や樹脂等も使用しています。
自動弁の機能を常に保持するためには定期的なメンテナンスが重要です。日常点検のほか、1年1回の目視等による点検(圧力計、騒音、振動など)、3~4年経過するとスケールによる摺動不良やゴム部材は経年変化や水道水中の塩素によるゴムの劣化等があり分解点検を推奨します。点検結果によって一般手入れ(スケール除去等)や主にゴム部品の交換等によって更新できます。
特に、受水槽等の緊急遮断弁は万一の機能確保のため、6 ヶ月~1年に1回の作動確認、制御盤内蔵バッテリーの寿命確認(定期的交換)が重要です。
また、電気温水器等の温水器用逃し弁は固着による缶体破損を防止するため、月1回程度のレバーによる作動確認、長期間不在時の使用前のレバーによる作動確認は重要です。(使用者による確認になりますが、レバー部または給湯器内の取扱い説明書に明記されています)
自動弁に関する使用上の問題点、メンテナンスなど、どのような事でもご相談に応じます。 |